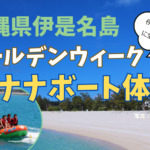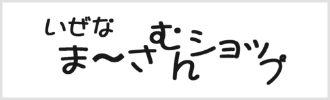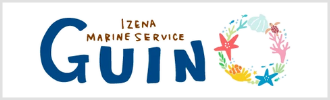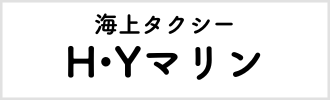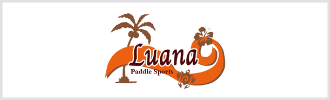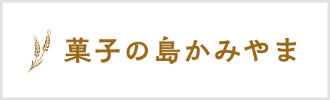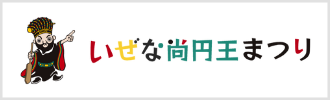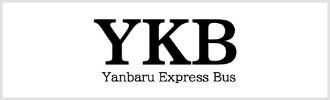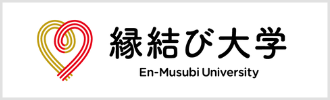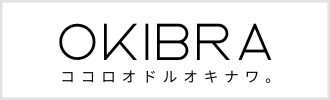沖縄には教育旅行の受け入れ先が数多くあります。民泊、農業体験、文化学習、SDGsプログラムなど、どれも魅力的な選択肢です。でも、それらを比較していく中で気づいたのが、伊是名島はただの「体験の場」ではなく、体験を通じて『自然に学びが起こる』環境があるということ。
楽しかった、面白かったで終わらない。生徒が自分の中で「何か」を感じて、言葉にして、行動につなげるような流れが、島の時間の中にあるのです。
体験ベースのプログラムなのに「思考」が自然に動き出す
伊是名島の教育旅行では、体験が『学び』に変わるきっかけがあちこちにあります。三線を弾く、畑を耕す、料理を作る。そのどれもが「なぜこうしているの?」「これって自分の暮らしとどう違う?」という気づきを引き出してくれます。特別な問いかけや設計をしなくても、ホストとのやりとりや、体験の背景にある暮らしそのものが、生徒の『思考のスイッチ』を自然に押してくれる。だからこそ、「考える力」が無理なく育つ場になっているのです。
『地域と学びが地続き』だから、学びに説得力がある
他地域では、教育旅行用に用意された施設や体験プログラムが主になることも少なくありません。対して伊是名島では、体験そのものが地域の日常に根ざしています。訪問先の畑は、ホストが毎日働いている場所。三線を教えてくれるのは、地域の祝い事で実際に演奏している方。つまり、学びが「リアル」なんです。『作られた学習』ではなく『暮らしの延長にある学び』だからこそ、生徒の心にスッと入ってくる。そこに説得力があります。
人との関わりが、学習効果を『自分ごと』に変えていく/h2>
伊是名島では、人との距離が近い。ホストとの共同生活、地域とのふれあい、そして先生との対話の中で、生徒たちは自然に自分の言葉で考え、表現するようになります。それは「学んだこと」ではなく「自分の中で気づいたこと」
このプロセスが、ただの体験を『学習』に変える大きな鍵です。教育的に見れば、これは『主体的な学び』が自然に起きている状態。まさに今、教育が目指す方向性そのものです。
伊是名島の教育旅行は『学びの循環』が生まれる場所
生徒が体験して、感じて、考えて、話して、振り返って、また動く。
この『学びの循環』が自然に流れているのが、伊是名島のすごいところです。教員が意図しなくても、場の力と人との関係性の中で、生徒の「学び続ける力」が引き出されていく。旅行から帰ったあとも、レポートや感想文の中で、成長の片鱗が垣間見える。伊是名島は、教育旅行というフィールドにおいて『考える力』を育てる本物の場所だと言えます。