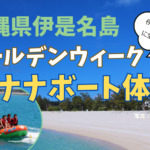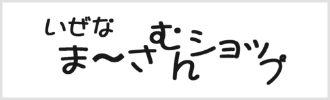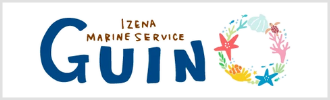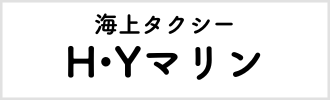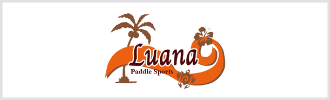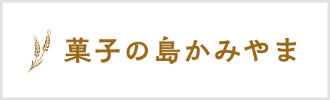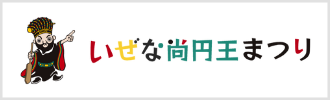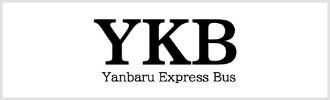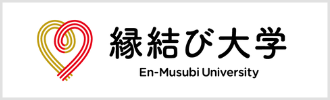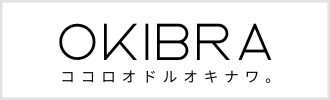沖縄で修学旅行に民泊を取り入れようと思ったら、受け入れ先の選択肢はたくさんあります。でも、「文化交流の深さ」という一点で比べたとき、伊是名島は群を抜いています。観光型の体験やスケジュール通りの活動ではなく「人と人が向き合う時間」がちゃんとある。生徒たちが『誰かと出会い、自分と向き合う』体験ができる場所。それが、伊是名島の民泊なんです。
他地域との大きな違いは『つながり方』の質にある
本島や他の離島でも民泊はできます。でもよくあるのは、用意された体験をこなして、時間で解散して、ちょっと会話して終了。伊是名島は、そうではないです。ホストと一緒に過ごす時間そのものが長くて深い。ご飯を作る、洗い物をする、ちょっと世間話をする。その『なにげない時間』こそが、文化交流の本質です。
『文化を教える』ではなく、『文化と一緒に過ごす』から深い
伊是名のホストさんは「教えてあげよう」というスタンスではないです。一緒に過ごして、一緒に作って、一緒に笑う。その中で「それどういう意味?」「なんでそうするの?」って自然に会話が生まれる。つまり『文化を学ぶ』ではなく『文化の中に入る』体験ができる。それが伊是名の民泊のすごいところ。
交流が『最後のあいさつ』で終わらない、本当に心が動く関係になる
「ありがとうございました」で終わる民泊も多い中、伊是名では「また会おうね」「連絡してね」という関係が自然に生まれます。ホストの家に手紙を出したり、翌年の卒業旅行で再訪したり、SNSでつながっていたり。生徒にとって『誰かと出会った』という実感が残る。これはただの体験じゃなくて、人生の中の「関係」が生まれるってことなんですよ。
島全体で文化を守ってきた『空気』が、体験の深さをつくっている
伊是名島は、ただ自然がきれいとか、歴史があるとかじゃないんです。『人が文化を今も守ってる』空気が、島全体にあります。三線の音がどこかから聞こえてくる、夜になると星を見ながら昔話が始まる、道で出会った人がふつうに話しかけてくれる。そういう全てが、生徒たちの感性を揺さぶってくれる。伊是名では、文化が「体験プログラム」じゃなくて「日常」なんです。